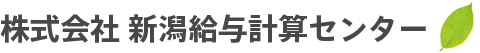AIにはできない労務相談―真因を見抜くのは人間
2025年に入り、生成AIが本格的に活用されるようになりました。
労務問題についても、AIによる回答を目にする機会が増えています。
確かにAIは、労働基準法をはじめとする労働諸法令や過去の裁判例など、さまざまな角度から根拠を示し、多方面から回答してくれます。
しかし、難しい労務相談というものは、相談する経営者や会社側が「真の原因(真因)」をつかめていないまま、表面的な質問だけを投げかけている場合が多くあります。
そのような状況でAIに質問しても、AIはその質問の範囲で素直に答えるだけです。
AIは決して否定せず、謙虚で、素直で、正確に回答しますが、質問者の理解や情報の範囲を超える答えは返してきません。
つまり、質問のレベル以上の答えも、以下の答えも出てこないのです。
「難しい労務相談はAIにはできない」と言い切れるのは、質問する側が会社の現状を客観的にAIへ伝えきれていないからです。
たとえば、問題のある労働者をなぜ採用したのか、どのような経緯で採用したのか、入社後にどの上司からどんな指導を受けてきたのか、その労働者の仕事ぶりや上司の対応はどうだったのか、といった具体的な情報がAIに与えられていないことが多いのです。
特に会社側に不利となる情報を意図的に省いたまま相談しても、AIが正確な判断を下すことはできません。
AIはあくまで一般的な法律や判例を基に、与えられた質問のレベルに応じた回答を返すだけです。
AIにできないことは、「人間が状況判断する瞬時の情報」と「直観力」の二つです。
たとえば、ある労働事件の裁判例を読んだとしても、その背景事情や当事者の関係性までAIに入力しない限り、AIはその本質を理解できません。
難しい労務相談をする会社側の過去の詳細な経緯をインプットしない限り、AIの答えはいつまでも一般論にとどまります。
こうして見ると、難しい労務相談に関しては、AIが答えることには限界があることがはっきりしてきました。
AIは非常に優れたツールですが、最終的に現場の状況を読み取り、判断を下すのは人間の役割です。
AIが提示する情報をどう受け止め、どう活かすかは、やはり人間の経験と直感に委ねられているのです。
令和7年10月1日 水谷英二の経営者に一言
今月のテーマは、「AIにはできない労務相談―真因を見抜くのは人間」でした。